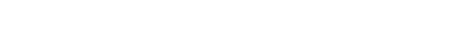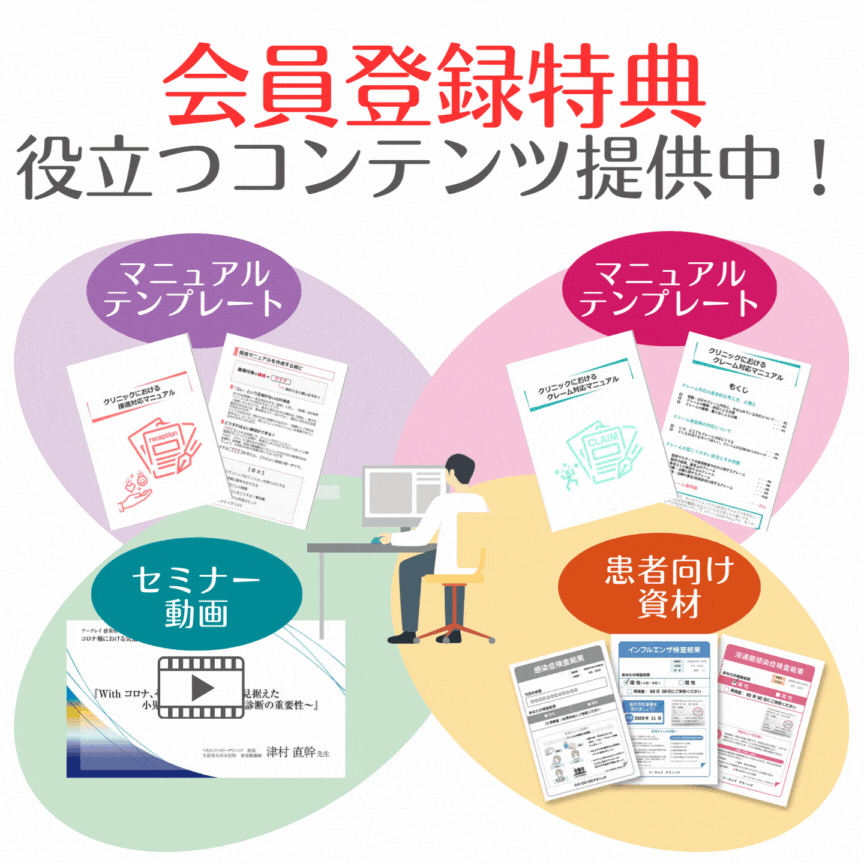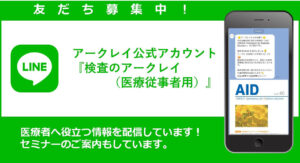「患者さんからの予想外の要望で困った」
このような経験はないでしょうか?
クリニックでの対応を
事前に決めておけば、
いざというときにスムーズに対応できます。
そこで本記事では、
クリニックにおける医療接遇を
場面ごとに分けて解説します。
また、自院で「接遇対応マニュアル」を
作成する際のポイントもご紹介しています。
本記事は会員向けコンテンツ
「接遇対応マニュアル」の内容を
抜粋してお伝えしております。
ダウンロードには
会員登録またはログインが必要です。
会員ページはこちらから
※ご注意!:本記事は、『前編:医療接遇を極める!「考え方と基本的事項を解説します」』の続きです。
先に前編の記事をご一読いただくことをおすすめいたします。
場面ごとの医療接遇
一般的な診療場面ごとに
医療接遇の例をあげています。
以下にあげる医療接遇のポイントを参考に
自院でできる対応を検討してみてはいかがでしょうか。
※より詳しい事例集は
「接遇対応マニュアル」14ページでご紹介しています。
⇒会員ページ(無料)に移動します
受付
来院された患者さんは、多くの時間を
受付スタッフが担当する場所で過ごします。
そのため、受付での対応は、
クリニック全体の評価に大きな影響を
与えることにつながります。
受付対応のポイントは以下の3つです。
1. あいさつ
2. 患者さんの様子を観察する
3. 待ち時間の案内
例)
高齢の患者さんが来院された際、
介助が必要な場合があります。
受付時に必要なスタッフを配置できれば
その後の診察もスムーズになります。
診察前後
診察を受ける前後でも注意したいことがあります。
患者さん一人ひとりに合う接遇のために
以下の4つポイントに注意しましょう。
1. 患者さんの呼び方
2. 貴重品を待合室に置いたままにしないよう声がけ
3. かさばりやすい冬のアウターの対応
4. 診察後のあいさつ
例)
診察後に患者さんに
「お大事になさってください」
と声をかけたことはないでしょうか?
患者さんはそれ以上を求めていないかもしれません。
しかし、たった数秒で
「あなたを大切に思っています」
と伝えることができるなら、
言い換えの工夫がもたらす効果は
大きいのではないでしょうか。
診察介助
患者さんへの声かけは、
例え子どもや高齢者で付き添いがいても、
常に患者さん本人を対象とすることが大切です。
理解できなくても簡単な言葉で説明し
気持ちを和らげるよう心掛けましょう。
検査
採血やレントゲンなどの一般的な検査は、
多くの患者さんが経験しているでしょう。
しかし、「知っているだろう」と思わずに対応することが大切です。
また、患者さんの理解度に合わせて、
医療用語などの言葉を避けて説明が必要です。
会計
「終わりよければ全てよし」
と言いますが、
会計の接遇が良いと、
患者さんはクリニックに対して
良い印象をもつことができます。
逆に、診察まで満足していたのに、
会計で納得できないと、
「もう来たくない」と思わせてしまいます。
会計の場面においても
患者さんの表情に気を配ることが大切です。
電話
電話は声のみのコミュニケーションです。
相手の表情や状況が分からない
ということを意識して、
対面で話すときよりも、
ゆっくり・はっきり話すことを
心掛けましょう。
電話を受けた際に、
他スタッフに伝言が必要な場合は、
以下の3つのポイントを意識すると良いでしょう。
1. 患者さんの話をさえぎらない
2. 5W3Hをおさえて復唱
3. 折り返しの電話が必要な場合は期限を伝える
業者対応
クリニックの待合室の患者さんは
スタッフの業者対応を診ていることが多いです。
業者と患者さんへの態度が明らかに異なる場合、
患者さんは不信感を覚えるかもしれません。
そのため、業者への態度も
患者さんと同じにすることがポイントです。
こんなときどうする?事例集から一部ご紹介
クリニックで以前に困った事例や
事前に考えられる事例などを
スタッフ同士で話し合い、
共有すると良いでしょう。
また、必要に応じて、自院に合った
マニュアルの作成が必要です。
「接遇対応マニュアル」の事例集から
2つの事例をご紹介いたします。
その他にも具体的な事例を複数掲載しています。
詳しくは会員ページ内にある
「接遇対応マニュアル」をご確認ください。
⇒会員ページ(無料)に移動します
受付での事例:保険証忘れ
保険証を忘れた場合、原則的には全額自己負担となります。
後日、保険証を提示して精算可能ですが、
問題は保険証を忘れた際の所持金が
不足している場合です。
医師法第19条の「応召義務」により、
医師は患者さんの診療を拒否することができません。
つまり、患者さんの所持金不足を理由に
診療を拒否することはできないということです。
※医学的な治療を要さない自由診療を除きます。
このような患者さんに対して、
全てのスタッフが同じ対応ができるよう、
精算方法の説明パンフレットを用意し、
クレーム対策することが大切です。
診察での事例:症状の訴えが曖昧で、主訴が把握できない
患者さんは医療従事者ではありません。
自身の症状について的確な表現ができない場合があります。
まずは、患者さん本人の話を聴き、
一緒に整理するつもりで関わりましょう。
痛み・痒み・痺れ・違和感など
客観的に評価しにくい症状を
「ピキッと」「ズズーん」「カチカチ」
のような独特の表現で訴える患者さんもいます。
患者さんの症状は本人の言葉で表現したものが一番正しいと言えます。
カルテにはそのままの表現を記載することが望ましいでしょう。
マニュアル作成のヒント
スタッフ同士が共通の認識を持って
医療接遇の対応ができるよう、
マニュアルを作成することをおすすめします。
マニュアル作成の際は
以下の5つがポイントとなります。
1. クリニックのミッションが見える状態で作成する
2. 完璧を目指さない
3. 1つの項目はA4で1枚にまとめる
4. 具体的な表現にする
5. 否定的な表現は避ける
詳しくは会員ページ内にある
「接遇対応マニュアル」をご確認ください。
⇒会員ページ(無料)に移動します
まとめ
これまで、医療接遇に関して、
会員ページ(無料)に掲載している
「接遇対応マニュアル」の内容を
前編と後編に分けて解説してきました。
理想のクリニックとは何か
患者さんはクリニックに何を願うのか
院内スタッフに何を望むのか
自院に合ったマニュアルを作成し、
患者さんに寄り添った接遇ができるよう
ぜひ、ご活用ください。
「医療接遇」に関するコンテンツは
会員ページ(無料登録)にログイン後、
ダウンロードください。
「クリニックにおける接遇対応マニュアル.pdf」
「接遇対応マニュアル_チェックリスト.pptx」
「接遇対応マニュアル_テンプレート.pptx」
「電話対応_確認ポイント_テンプレート.pptx」
患者さんへの情報提供に重要な院内ポスターですが、「デザインに自信がない」「作成時間がない」とお悩みではありませんか?今回は、無料ツールを活用して、多忙な医療従事者の方でも短時間で簡単に、効果的なポスターを作成する方法をご紹介します。
#アークレイ
クリニック経営にトラブルはつきものですが、全て弁護士に頼るのが最適とは限りません。コストや専門性を考慮し、内容に応じて適切な士業を選ぶことが重要です。そこで今回は、トラブル別に、弁護士の他にも頼れる専門家の相談先をまとめました。
#アークレイ
かつて法的規制があったオンライン診療は、コロナ禍を経て普及が進んでいます。広域な集患等の利点がある一方、セキュリティやコストへの懸念から導入を迷うクリニックも多いです。本記事では、最新の保険点数動向や導入の是非について詳しく解説します。
#アークレイ