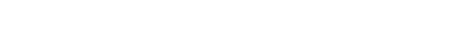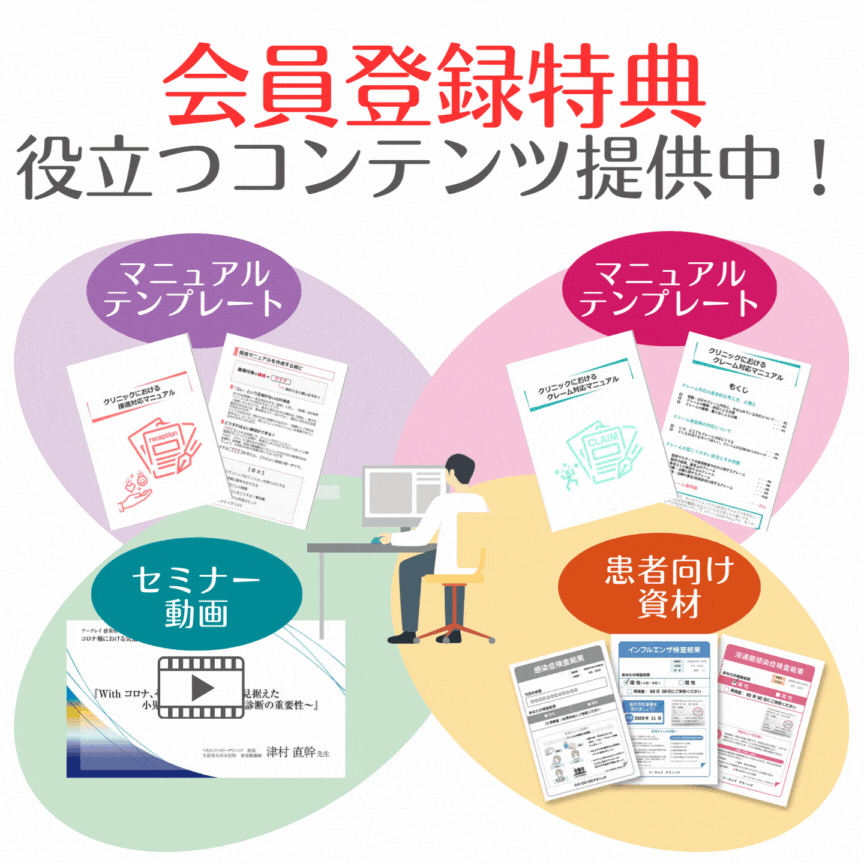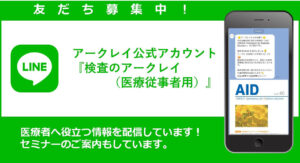前編:ペイシェントハラスメント「クリニックが知るべきポイント」 はこちら
ペイシェントハラスメント(ペイハラ)は
近年増加の一途を辿っています。
ペイハラの内容も悪質化しており、
2022年埼玉県ふじみ野市で医師が
訪問診療先で射殺された事件など、
生命に関わる事案も報告されています。
最近では、事故を起こした芸能人が
搬送された病院で看護時に暴行を加え、
逮捕される事件の報道もあり、
ペイハラ対策に関心が高まっています。
後編となる今回は、
ペイシェントハラスメントに対して
今すぐできる具体的な対応策を
ご紹介します。
本記事は、『前編:ペイシェントハラスメント「クリニックが知るべきポイント」』の続きです。先に前編の記事をご一読いただくことをおすすめいたします。
ペイシェントハラスメント対策の鉄則
ペイハラ対策の鉄則
「治療中の患者さんだからといって迷惑行為が許されるわけではない」
患者さんの中には残念ながら
「自分が病気で辛いから医療機関は
自分の要望を何でも聞く必要がある」
と考えている人も一定数おられます。
一方で医療関係者の中には
「病気だから仕方がない」
などと言って泣き寝入りする人も
少なくありません。
しかし、「病気で治療を受けているから」
といって他人に迷惑をかけて良いわけではありません。
クリニックのスタッフ全員が
この鉄則を十分に理解し、
ペイハラ対策を進めていきましょう。
具体的なペイシェントハラスメント対策の立て方
具体的なペイハラ対策は、
以下の3つのフェーズに分けて考える必要があります。
1. 日頃の備え(予防)
2. 発生時の対応
3. 発生後の対応
1. 日頃の備え(予防)
日頃の備えとしてまず行うことは、
ペイハラ対策実施の周知と院内ルールの明確化です。
院内の掲示やホームページで
ペイハラに該当する行為を具体的に明記し、
「自院ではそのような行為を許容しない」
「暴言・威嚇・迷惑行為などを行った場合は
診療をお断りすることがある」など
クリニックでの対応を明記したポスターを
院内に掲示すると良いでしょう。
院内アナウンスや待合室のモニターで
定期的に流すだけでも周知の効果があります。
ペイハラや迷惑行為に対する規定や
指針・マニュアルなどの対応フローなどを
整備していないクリニックは、
早めに整備を行いましょう。
以下の内容をまとめて
スタッフ全員に共有しておくと、
対応の差を減らすことができます。
・クレーム対応の基本
・暴言を受けた場合の初動
・暴力など危険な行為を受けた場合の手順
また、対応の差を減らすことで
対応が弱いスタッフに迷惑行為が集中するリスクを減らすこともできます。
すでに要注意の患者さんがいる場合は、
最寄りの警察署や顧問弁護士などに
事前に相談をしておくと良いでしょう。
また、「迷惑行為チェックリスト」などで
どのレベルのペイハラなら相談するべきか
の基準を統一しておくと、
いざという時に早めの対応をすることができます。
2. 発生時の対応
実際にペイハラが発生した場合、
最も重要なのは、落ち着いて毅然とした態度で臨むことです。
初期対応が不適切であった場合、
さらなるペイハラを誘発する危険性があります。
また、事前に決めたフローに従い、
院内各所のスタッフを集めるとともに
警察に通報するかを検討してください。
暴力行為や相手が刃物を持っているなど
生命や身体に明らかな危険が及ぶ場合は、
院内スタッフや患者さんの
安全確保を最優先で行い、
躊躇わず警察に通報します。
また、怪我をした場合などは、
必要に応じて応急処置を行い、
他院へ受診が行えるよう手配しましょう。
現場や証拠の保全も重要です。
損害賠償請求など法的措置をとる場合は、
証拠が重要となります。
例えば怪我人が出た場合は、
怪我をした部位の写真や
聞き取りの記録(録音など)、
受診した場合は診断書や領収書などを保存しておきましょう。
院内の設備を壊された場合は、
壊れた場所の写真や聞き取りの記録のほか、
修理の見積書や請求書・領収書などが必要です。
3. 発生後の対応
ペイハラが発生したら、
まずは迷惑行為を受けたスタッフのケアを行う必要があります。
怪我などがなくても、精神的に大きな傷を負っていることがよくあります。
直接的な離職の原因になりますので、
カウンセリング等含めた積極的な対応が必要です。
またペイハラを行った患者さんに対し、
必要に応じて通告を行います。
通告を行う基準は、あらかじめ対応フローの中で決めておきます。
通告した内容が記録として残るように、文書で行いましょう。
発生した事例については、
院内スタッフやその他関係部署で共有し、
原因究明や再発防止策を検討することで、
再度ペイハラが発生した際に、
スムーズに対応できるようようにしておきます。
まとめ
以上、ペイハラへの具体的な対応策をまとめました。
ペイハラ発生後の対応も重要ですが、
ペイハラが起こりにくいクリニックを
作り上げることが最も大切なことです。
一度発生した事案に対しては
莫大な時間やお金、労力が費やされるかもしれません。
しかし、発生を未然に防ぐ対策は
それほど手間がかからないものがほとんどです。
また、院長自らが、
ペイハラに毅然と対応するという姿勢を
院内外に見せることだけで、
スタッフは安心して働くことができるようになります。
まずは、今すぐにできることから始めてみると良いかもしれません。
医師 M.M.
参照元:厚生労働省「医療従事者の勤務環境の改善について」
医療現場及び訪問看護における暴力・ハラスメント対策について
厚生労働省 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル