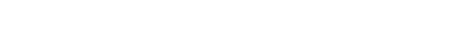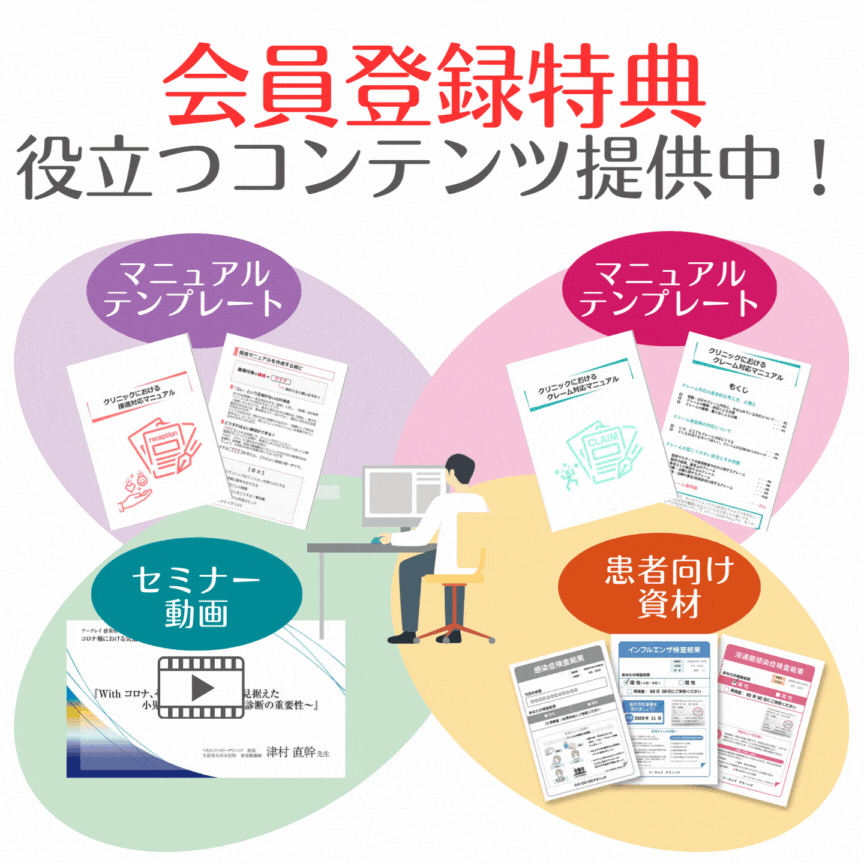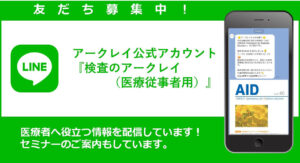昨今、患者さんやご家族からの
過度な要求や理不尽なクレームに
悩むクリニックが増えています。
これらの行為は、
顧客等からの著しい迷惑行為
いわゆる「カスタマーハラスメント」
(カスハラ)と同様に、
「ペイシェントハラスメント」(ペイハラ)
と呼ばれています。
厚生労働省では、各企業に対して
カスハラ対策を求めており、
対策マニュアルなども作成されています。
参照元:厚生労働省「「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を作成しました!」
そのため、小規模のクリニックでも
ペイハラ対策は急務と言えます。
そこで今回は、
ペイシェントハラスメントの話題を
前編・後編に分けてお届けします。
前編となる本記事では、
ペイシェントハラスメントの定義や類型、
具体例のご紹介とともに、
クリニック経営に与える影響や
対応策のポイントについて
簡単にまとめました。
ペイシェントハラスメントとは
『ペイシェントハラスメント』
通称『ペイハラ』とは、
医療機関や医療従事者が、
患者さん及びその家族等から受ける
迷惑行為のことを言います。
たとえば新潟県では、県の病院局が、
「ペイシェントハラスメント対策指針」を
2024年5月に独自に策定するなど、
各地でペイシェントハラスメントの
対策に関する動きが高まっています。
「厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、
ペイシェントハラスメントは多くの医療機関で以下のように定義されています。
「患者・家族等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、病院職員の職場環境が害されるものをいう」
ペイシェントハラスメントの類型と具体的な例
ペイシェントハラスメントと一言でいっても、
その内容は多岐に分かれます。
ここでは、新潟県病院局が作成した
「ペイシェントハラスメント対策指針」から
その内容を簡潔にまとめました。
① 暴言型
怒鳴り声をあげる、
「馬鹿」などといった侮辱的な発言、
人格否定・名誉を毀損する発言、など
② 暴力型
殴る、蹴る、物を投げる、
物を壊す、わざとぶつかる、など
③ セクハラ型
過度なボディタッチ、
性的行動・発言、ストーカー行為
(LINEなどの個人情報を聞く、
待ち伏せする、必要性のない頻回の受診・面会など)など
④ 時間拘束型
長時間にわたり職員を拘束する、
居座る、長時間の電話、
他院の文句など自院では対応できない内容の話を延々とする、など
⑤ リピート型
病院からの説明後に電話や面会などで
理不尽な要望を繰り返し要求する、
郵送・FAXなどで同じ内容を繰り返し質問する、など
⑥ 威嚇・脅迫型
「殺されたいのか」などの脅迫的発言、
反社会的勢力との繋がりをほのめかす、
必要以上に接近し病院職員を怖がらせる、
「対応しなければSNSに上げる」などの
ブランドイメージを下げるような脅し、など
⑦ 権威型
権威を振りかざして要求を通そうとする、
執拗な特別扱いの要求、
謝罪文や土下座の要求、など
⑧ 院外拘束型
患者さんの自宅や特定の喫茶店等に
医療スタッフを呼びつける、など
⑨ SNS/インターネット上での誹謗中傷型
患者さん個人の自己要求の実現や
医療スタッフへの批判を目的として、
動画撮影する行為、
インターネットやSNS上に
医療スタッフの名誉を棄損または
プライバシーを侵害する情報を掲載する行為、など
ペイシェントハラスメントがクリニック経営に与える影響
ペイシェントハラスメントへの対応は
スタッフの精神的な負担が極めて大きく、
業務効率を低下させるとともに
休職・離職の原因となります。
また、クレーマーがいると言う噂が広まれば、
募集をかけてもスタッフが集まらず、
人員不足が恒常化するとともに
スタッフの質が低下する恐れがあります。
医院運営の面から考えると、
実際、クレームに対応している時間は
何も生み出しません。
対応にスタッフの手を取られれば、
診療をはじめとした他業務ができず、
通常業務に支障が生じます。
問題が深刻化すれば、対応策の検討、弁護士・警察など
外部との相談などにも多大な時間を浪費します。
また、弁護士はじめ外部の助けを借りると余分なコストが発生します。
もちろん、クレーマーの存在は、
人材の確保や医院運営だけでなく、
集患にも当然影響をしてきます。
大声でクレームを言う患者さんや
その家族等がいた場合、
院内の雰囲気を損ね、
自院に対するブランドイメージを大きく低下させます。
特に小規模クリニックの場合、
口コミも重要な集患対策となりますので、
口コミによるブランドイメージの低下が
クリニック経営に致命的な影響を与える可能性もあります。
ペイシェントハラスメントへの対応策のポイント
ペイシェントハラスメントと
思われる事案が起こった際は、
クリニック経営者はまず
「院内スタッフを守る」ことを
第一に考えて行動する必要があります。
そのためには、普段からスタッフに対し
「ペイシェントハラスメントは個人ではなく
組織として対応するものである」ことを
徹底して周知することが大切です。
また、直接対応する看護師等の
医療スタッフや受付等の事務職員、
クリニックの管理部門である院長や事務長、
法的な視点で助言・対応を行う顧問弁護士、
その他、自院に関係する全てのスタッフが
情報を密に共有し、統一した方針の元で
対応できる組織作りを行いましょう。
実際に対応が必要になった際には、
理不尽な要求には屈せず
毅然とした態度で対応すること、
犯罪に該当する可能性のある行為
(暴力や脅迫など)については
躊躇わずに警察の介入を求めること
が重要なポイントです。
まとめ
今回はペイシェントハラスメントについての
基礎知識を簡単にまとめました。
ペイシェントハラスメントは放置すると、
スタッフの離職に直接つながるとともに、
クリニックの雰囲気を悪くし
患者さん離れの原因となりえます。
ペイシェントハラスメントは
起こってから対処するのではなく、
ペイシェントハラスメントが起こりにくい環境を構築することが大切です。
具体的な対応策については
次回の後編の記事に詳しくまとめますので、
ぜひ、そちらもご参照ください。
医師 M.M.