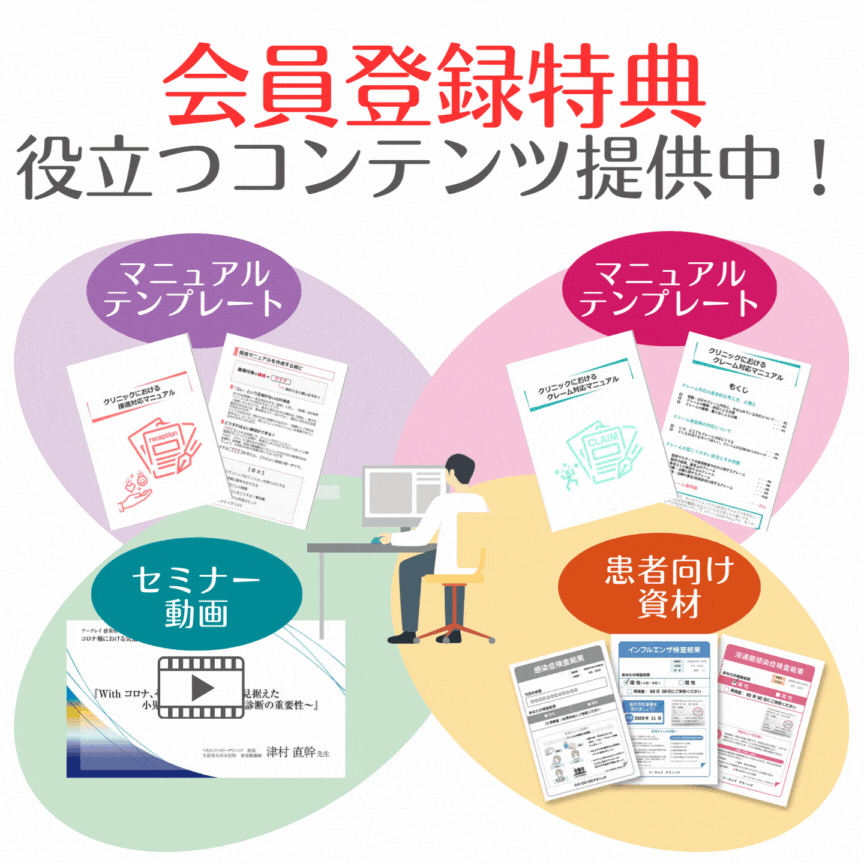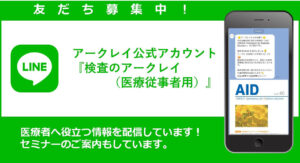選ばれ続けるかかりつけ医になるために、
待ち時間対策は欠かせません。
- Web予約システムを導入する
- 業務を見直して無駄を省く
- 待合室をラグジュアリーな空間にする
- 患者さんが楽しめそうなコンテンツを用意する
かなりの具体策がありそうです。
今回はこれらを始める前に、
そもそも患者さんにとって
「待つ」とは何なのか?という話題です。
マイスターの8つの法則
経営実践があり、
プロフェッショナルサービス会社経営の
専門家であるデービッド・マイスター氏が
提唱した法則をご紹介します。
1985年に論文『The psychology of waiting lines』において、
待ち時間を長く感じる法則を説明しました。
- 何もしていない時間は長く感じる
- 人はとにかく何かに取りかかりたい
- 不安があると、待ち時間は長く感じる
- 待ち時間が分からないと、長く感じる
- 理由もなく、待ちたくない
- 不平等な待ち時間は長く感じる
- 価値あるものに対する待ち時間には寛容になれる
- 独りの待ち時間は長く感じる
この法則から、大半の患者さんは待ち時間を
長く感じる可能性が高いことが分かります。
- 体調が悪い時に読書やネットサーフィンを
しながら待てない - 自分の病気への不安がある
- 待合室に患者さんはたくさんいるけれど、
自分が何番か分からない - 明らかに診察室には誰もいないのに、
次の患者さんが一向に呼ばれない - 自分より遅く受付をした人が
自分より早く診察室に入る - 小児や要介護者でなければ1人で受診する
医療機関であれば、このようなことは仕方ないかもしれません。
しかしクリニックは、待ち時間を
長く感じさせる要素が多いと、
改めて認識することが大切です。
これだけすればいい!という対策はない
残念ながら、全てのクリニックに万能な対策はありません。
一口に「待ち時間」と言っても、
実際の待ち時間と患者さんの体感的な待ち時間があるからです。
エレベーターは1分を超えると、
コンビニのレジは5分あたりから、
通勤電車の遅れが10分で、
イライラする人が増えるというデータがあります。
引用元:時計メーカーCITIZEN「ビジネスパーソンの「待ち時間」意識」2023年
つまり、人は「何で待たされるか」によって反応が変わります。
さらにその人の心身の状況にも左右されます。
待ち時間のイライラは
多くの要素によってもたらされ、
その要素1つを取り除けば
解決するものではありません。
待ち時間はクリニックだけでなく、
接客業においては最大のテーマです。
一筋縄ではいかないのです。
それどころか、安易な対策は効果をもたらしません。
対策が水の泡にならないためにも、
しっかりと検討した上で導入すると良いかもしれません。
まずは現状把握から
待ち時間対策をするために、
患者さんを把握することから始めるのはいかがでしょうか。
ここで考えがちなのは、患者満足度アンケートです。
実際に本人に聞くことが確かなのですが、
患者さんにご面倒をおかけすることになります。
まずはスタッフへの聞き取りと、
クレーム内容の検討が良いかもしれません。
特に受付スタッフは重要な存在です。
患者さんの待っている様子を見ることができるからです。
- 会計の際に明らかにイライラしている人が多い
- 辛そうに座っている患者さんを見かけている
などクレームも丁寧に検討していきます。
待ち時間に対するクレームでなくても、
待ったことによってイライラが助長された
患者さんもいるかもしれません。
1人の患者さんが受付をした時間、
診察室に入った時間、
会計を終えてクリニックを出る時間を
記録してデータを収集するのも効果的です。
(ディズニーリゾートでは
アトラクションゲートで無作為にお客さんに
カードを渡し、乗車直前にその人から
カードを回収することで
正確な待ち時間を測定しています)
まずはスタッフで話し合うことから始めてみましょう。
まとめ
待ち時間対策はクリニックにとって重要です。
しかしテッパンな対策は存在せず、
クリニックの特徴に合った丁寧な対策が必要です。
患者さんの「待つ」という心理を理解し、
スタッフ間で現状把握することから
始めてみてはいかがでしょうか。
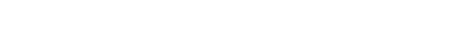







-150x150.jpg)