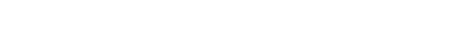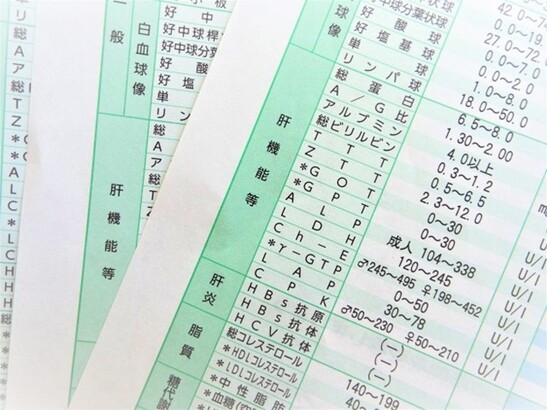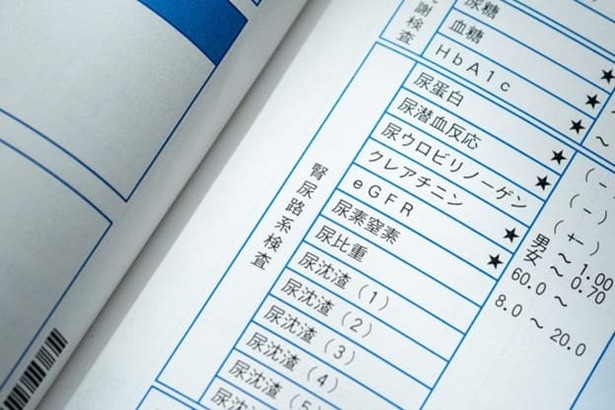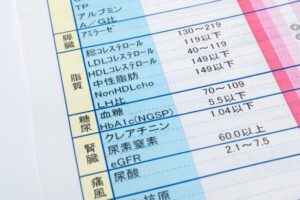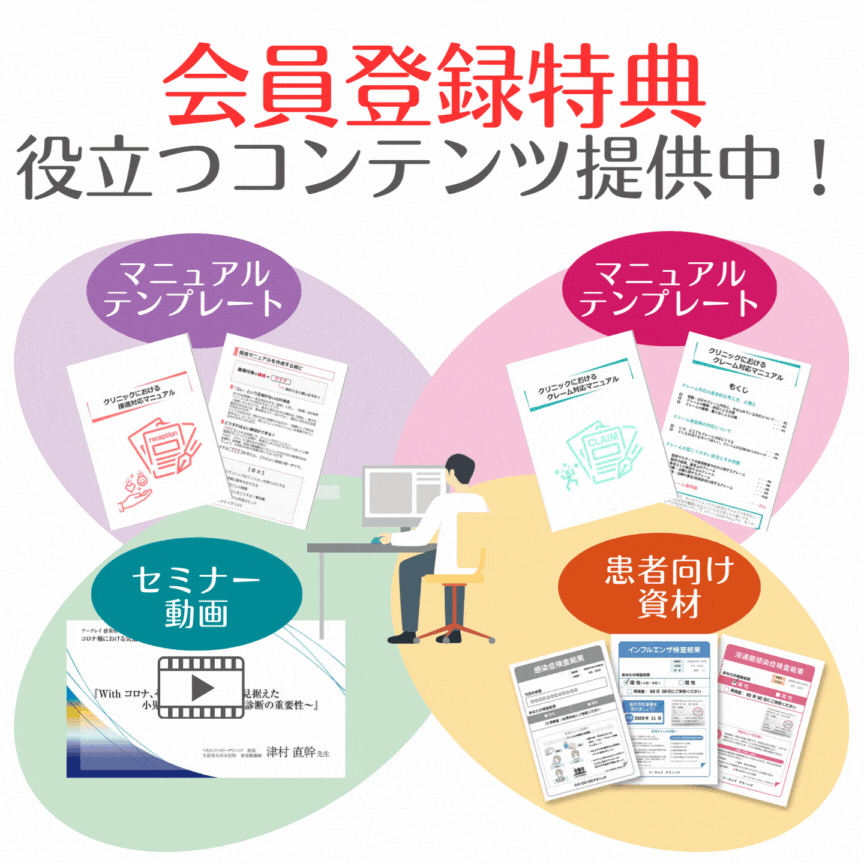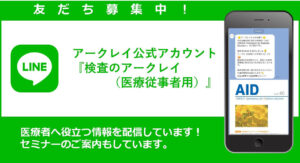冬は季節の変化に伴う院内環境の変化や
運用変更が重なり、
院内検査を実施する医療機関にとって
厄介な季節かもしれません。
室温の低下、湿度の低下、
屋外から持ち込んだ装置・試薬の温度差、
そして年末年始の停止と再立ち上げ。
これらが複合すると、測定誤差、再検、
検査装置のエラー、試薬劣化が
表面化しやすくなります。
そこで今回は、施設規模に関わらず、
様々な検査装置・試薬で考えられる
「低温・乾燥が与える影響と対処」
「年末年始にありがちなトラブルと予防」
を整理して、対策をご紹介します。
低温・乾燥が与える影響と対策
冬のトラブルは「低温」と「乾燥」が
原因であることが多いです。
その影響と対策について
6つのポイントをご紹介します。
1. 温度順応不足によるゼロ点ずれ
冬の屋外などの寒い環境から
室内へ運び込んだ検査装置は、
内部温度が安定するまでは
測定値が安定しにくくなります。
起動前に室温へ順応させる“待ち時間”を
ルール化すると良いかもしれません。
多くの検査装置は18〜28℃、
相対湿度20〜80%を推奨レンジとし、
最低15〜30分の順応で誤差を抑制できます。
急ぎの場面ほど、温度順応させることを
省かないことがトラブル回避の第一歩です。
2. 低温による反応速度低下と粘度上昇
低温下では試薬や検体の粘度が上がり、
分注・混合が不十分になりがちです。
吸光法・蛍光法など、光を使った測定で
結果値がばらつく原因の多くは、
実は“混ざっていない”ことです。
対策として、室温に戻す時間を規定化
(例:冷蔵品は取り出し後10〜15分静置)、
転倒混和の回数・速度を標準化し、
ピペットはエア抜き→試射→吐出確認をルーチン化します。
また、低温下では多くの化学反応が弱まります。
検査機器によっては、室温に合わせて
反応度を補正する機能を設けていますが、
装置・試薬を室温に馴染ませておく方が
誤差を軽減できます。
低温下ではピペット内部の
空気密度が変化し、吐出量がズレることもあります。
粘性の高いサンプルは吸引速度を落とし、
ピペットの空気密度やチップのロット間差の
確認のため、重量法での吐出試験を行い
(水を使った簡単な吐出量のチェック)、
ズレが一定以上なら校正・メンテナンスを検討します。
ピペットのOリングの乾燥硬化にも注意し、
薄くシリコン系潤滑を行うか、
消耗品交換も検討すると良いでしょう。
3. 乾燥による静電気と帯電不具合
相対湿度が40%を下回ると、
チップやチューブが帯電し、
微量分注や粉末試薬の取り扱いに影響が出ます。
・分注量の再現性低下
・粉が容器壁面に張り付く
・はく離紙が取りづらい
などの現象が典型的な例です。
検査室は湿度40〜60%の維持を目標に、
加湿器は「連日給水+タンク洗浄」
「週1でスケール除去」を運用に組み込みましょう。
作業をする際は、帯電防止マット、
導電性トレイ、帯電防止ブラシの併用が効果的です。
4. 結露と光学系の曇り・基板障害
屋外や寒所から搬入した装置は、
内部・光学窓・コネクタ部に
結露が発生しやすく、誤差やショートの原因になります。
移動直後は未通電のまま
防湿袋の外側で順応させ、
レンズ面は無塵ワイプで軽く拭き、
完全乾燥後に通電しましょう。
冷蔵庫から取り出した
光学セルやキュベットも同様に、
外面の水滴除去と室温平衡を経て使用します。
冷蔵庫内と室内の温度差を小さくするため、
壁面から離し、通気を確保する保管方法も有効です。
冷蔵保管していた試験紙類の開封にも注意が必要です。
室温平衡が不十分な場合、
開封時に吸湿して試薬が反応し、
測定結果に誤差を生む要因となり得ます。
試験紙はキュベットなどと違い、
結露の状況が判断しづらいため、
室温に静置する時間を十分に取りましょう。
5. 冷蔵品の取り扱いと開封後安定性
酵素・抗体・基質などは温度急変に弱く、
凍結厳禁の製品も少なくありません。
搬送時の保冷材は「直接当てない」
「保冷ボックス内に緩衝材を入れる」が基本です。
使用する際は、
「取り出し→室温平衡→使用→即時戻し」
を徹底し、開封日と使用期限をラベルで可視化します。
夕方などの診療終了間際に
試薬ボトルやキットを新たに開封して、
翌日に使えない残量を出さないために、
検査件数が少ない日は小分けバイアルや
少容量キットを選ぶなど、ロスを減らす運用も効果的です。
6. 冬季の品質管理(IQC)の考え方
環境変動が大きい時期は、
再立ち上げ当日のIQC
(Internal Quality Control:内部精度管理)
を強化することも大切です。
異なる濃度のコントロールを
2ポイント以上測定し、
日内2回(始業時と昼ごろ)の結果で
ドリフト(時間によるズレ)を確認します。
試薬ロットを切り替える場合は、
新旧ロットでのブリッジQCを行い、
平均値のシフトが許容範囲かどうかを
その日のうちに判定します。
値が外れたときは、
以下の①~④の順に原因を追っていくと
効率よく切り分けができます。
① 温度順応不足
② 分注・混和の不十分さ
③ 試薬劣化
④ 装置の光学系・温調
年末年始にありがちなトラブルと予防
冬のトラブルに加えて、
年末年始は長期停止と再立ち上げが重なり、
検査装置のエラーや試薬トラブルが
発生しやすい時期です。
ここでは、代表的なトラブルとその対策を整理します。
1. 停止前クリーニングの先送り
最終診療日は業務が集中し、
洗浄・廃液処理・ダスト除去が後回しになりがちです。
停止前日までにクリーニングを完了し、
当日は確認だけにしておくと良いでしょう。
洗浄ログ、廃液ボトルの空化、
フィルタ・ストレーナ点検、拭き上げ、
消耗品の封緘をチェックリスト化し、
担当者と完了時刻を見える化すると効果的です
2. 電源・バッテリー・UPS(無停電電源装置)の見落とし
長期停止中の瞬停や電圧降下は、
機器設定やデータの破損原因となります。
休日前にUPSの電池残量をテストし、
装置のバックアップ電池の残量確認と
設定ファイルのバックアップ取得を実施します。
完全シャットダウンする装置は、
再起動(例:通電→自己診断→温調安定→IQC)を
事前に確認し、年始の診療再開時に
余裕をもって準備できるようにします。
3. 冷蔵庫の温度逸脱とログ欠落
休診中は温度記録が抜けやすく、
試薬などを保管している冷蔵庫などの
温度逸脱の発見が遅れてしまいます。
自記温度ロガー
(温度推移を自動で記録できる小型計測器)
があることが理想ですが、ない場合は、
最低・最高温度表示の確認と記録、
ドア開閉防止のテープシール、
庫内の通風確保(詰め込み防止)で対応します。
診療再開時に疑義のあるロットは
外観・性能確認(QC優先)を行います。
4. 試薬の期限切れ・ロット混在による微妙なズレ
年内入荷と年明け入荷の試薬が混在すると、
同一日に実施した検査にロット差が発生し、
結果の解釈や比較がしにくくなります。
年末休暇前の装置を止める前に、
試薬期限が早いものから使えるように並べ、
診療再開初日はできるだけ
同じロットの試薬だけで、
コントロール測定し、その後、実検体を測定します。
やむを得ずロットが混ざる場合は、
旧ロットと新ロットで
同じコントロールの値を比較し、
値のズレを記録に残しておきましょう
5. 再立ち上げ時のウォームアップ不足
診療再開の初日にいきなり本稼働すると、
装置や室内環境が十分に安定しておらず、
エラーや再測定が増えて、
結果的に検査の進行が遅くなってしまうことがあります。
ISO 15189 などでは、
停止・再開時は手順を定め、
品質管理を行いながら段階的に運転を
再開することが求められています。
そのため再開日は、
「ゆっくり始めて、確実に立ち上げる」
ということを意識して、
以下の順番で段階的に立ち上げると良いでしょう。
例)電源を入れる
→ 室温・湿度が落ち着くのを待つ
→ 動きや異音を確認
→ コントロールを測る
→ 問題なければ、一度に検査する数を抑えて検査再開
→ その後、ルーチン検体測定の通常運転
特に光学測定や温度制御が重要な装置は、
内部の状態表示(ログ)が安定してから
本格稼働に入ると安心です。
6. 清掃・加湿器の衛生管理抜けによる二次リスク
加湿は必要ですが、不衛生な加湿器は逆効果です。
タンクは毎日洗浄・乾燥、
週1のスケール除去、
フィルタ交換時期の確認が大切です。
床・作業面の拭き上げは
帯電防止と毛羽立ちの少ないワイプを用い、
粉体やコントロール材の取り扱い時は
局所的な湿度確保も検討すると良いでしょう。
すぐ使える対策のポイント(要約)
- 室温18〜25℃・湿度40〜60%を維持。起動前の順応15〜30分を厳守。
- 冷蔵試薬は平衡→使用→即戻す。開封日と期限をラベルで可視化。
- 帯電対策に加湿+導電マット+帯電防止ツールを併用。
- 停止前の清掃・廃液・フィルタ点検・データバックアップは前日までに完了。
- 再開日は段階稼働。通電→自己診断→IQC→本稼働の順で“早さより確実に”。
まとめ:この冬を安定稼働で乗り切る
冬季の検査室運用は、難しい理論より
「環境を整え、手順を守る」ことに尽きます。
低温と乾燥に対する小さな配慮
(順応時間、湿度維持、帯電対策)と、
停止前後の基本
(清掃、バックアップ、段階再開、強化IQC)
を徹底するだけで、
誤差・再測定・機器トラブルは確実に減少します。
院内で『冬季モード』の標準手順を共有し、
ロットや測定系ごとで最小限の検証を実施、
この冬も安全・確実・再現性の高い検査を提供しましょう。