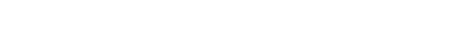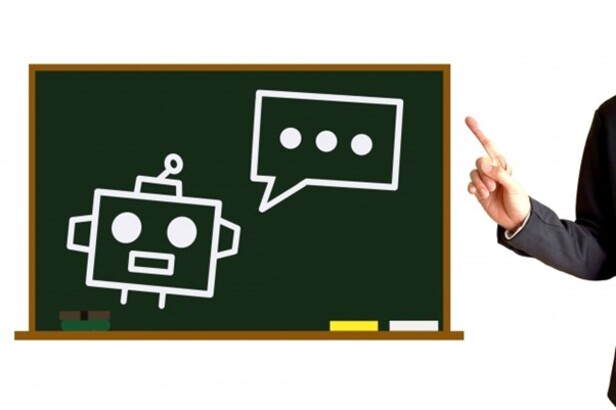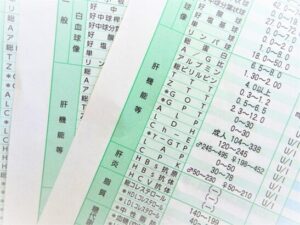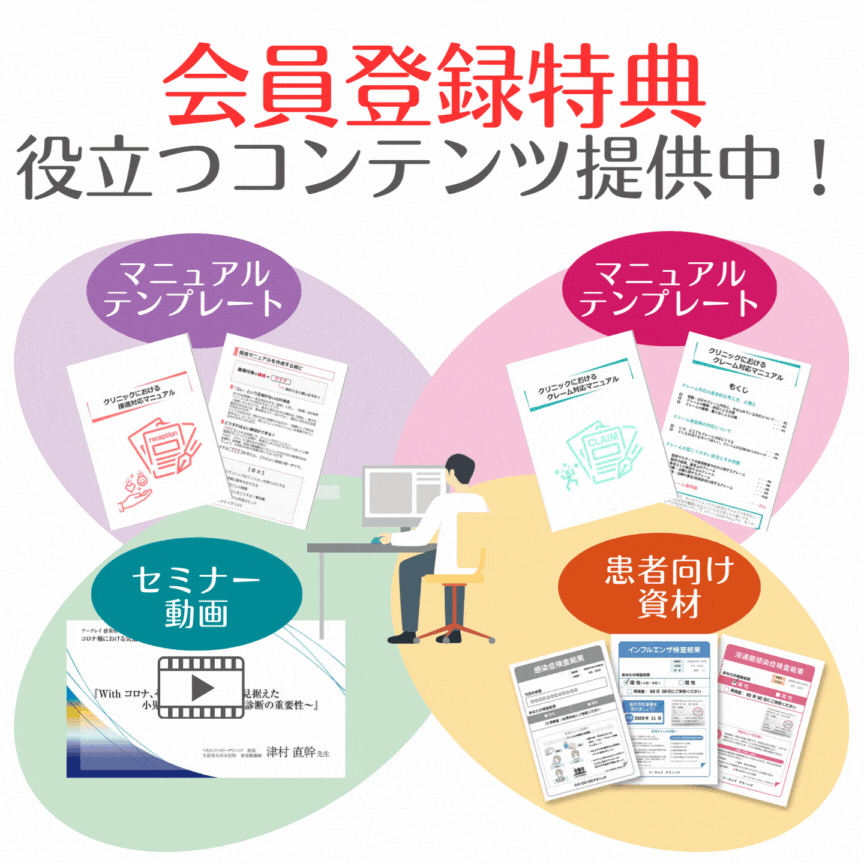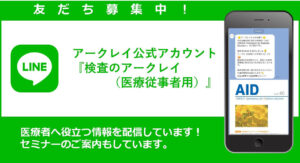昨今「AI (artificial intelligence:人工知能)」が
急速に進歩するとともに、
医療AIへの関心も急激に高まっています。
しかし、日経リサーチの調査によると、
AI医療機器の導入状況について、
まだ「導入していない」と回答した施設が
2023年では79%程度、
2025年では72%程度と、
大きく普及したとは言えない結果でした。
(2023年n=2,031名、2025年n=2,165名)
今回は、クリニックで医療AIの導入が
なぜ進んでいないのか、理由を掘り下げ、
医療AIを実際に導入するにあたっての
主な課題を2つに分けて、
解決策とともにわかりやすく解説します。
参照元:株式会社日経リサーチ「期待高まるAI、それでも8割の医療機関は未導入。理由は「費用対効果わからない」」
株式会社日経リサーチ「医療情報システム導入調査〈前編〉
なぜ医療AI導入は進まないのか
前述の日経リサーチにて、
医療AIを導入していない医療機関に
理由を尋ねたところ、
「費用対効果がわからない」51%
「費用対効果が良くない」24%
「保険収載」19%
と、コスト面を課題に挙げる方が大半でした。
また、その他にも
「AI利用に不安がある」23%
「利用シーンのイメージがわからない」20%
など、AI活用に関する不安が
払しょくできない方が多いことが分かりました。
不安の要素には、世間で言われるような、
「AIに仕事を奪われる」などのイメージが
先行していることも原因かもしれません。
課題①:AIは高額であり費用対効果が良くない?
確かに医療AIはどれも導入費用が高額です。
開業医の場合はクリニック存続のために
利益を出すことが至上命題となりますので、
一般的な医療の費用対効果を測る
「増分費用効果比(Incremental cost-effectiveness ratio: ICER)」
などの指標では、開業医が医療AIを
導入した場合の費用対効果を
うまく計算できないことも多いです。
医療AIの費用対効果を測る目安の1つとして
ROI(投資収益率)を用いると良いでしょう。
ROIとは、「投資した金額がどのくらいの利益を生み出したか」
をパーセント(%)で表示するものです。
ROI(%) = (利益 - 投資費用)÷ 投資費用 × 100
今回は、レセプトチェックを例に、
医療AI導入時のROIを検討します。
レセプトは明確な算定ルールと
標準化データに基づくため、
AIによる自動判定との相性がよく、
クリニックで導入しやすい医療AIの代表例といえます。
ROIは、AIを用いることで短縮された時間を
金額に変換することで算出することができます。
具体的には、
これまで医療事務スタッフに任せていた
レセプトチェックを医療AIに任せ、
医療事務スタッフの作業時間が
月に20時間削減できた場合のROIを以下に示します。
<計算例>
• 医事課職員の時給:2,500円
• 月間レセプト点検時間短縮:20時間
• 年間効果:20時間 × 12か月 × 2,500円 = 60万円
• システム費用:年間36万円
• ROI:(60万円 - 36万円) ÷ 36万円 × 100 = 66.7%
• 回収期間:36万 ÷ 60万 = 0.6年 (約7.2か月)
• 1年後の差額(純効果):60万 - 36万 = 24万 (投資額の約67%)
このように、医療事務スタッフの作業に
かかっていた経費60万円が削減され、
そのまま利益になると考えた場合、
ROIが大きくプラスとなっているので、
投資した金額に見合う利益が
得られていることがわかります。
また、7か月程で投資回収ができ、
その後1年時点では投資額の約67%が
純益として残ることがわかりました。
例で挙げたクリニックの経営状況からみると
積極的に導入すべきといった判断の目安となります。
ここで気を付けたいのは、
ROIで測れる指標は
あくまでも金銭的な利益のみであり、
それ以外のメリットやデメリットは測れないという点です。
例えば、以下のような内容は定量化することができません。
・毎月のレセプトチェックで発生していた時間外労働がなくなったことによる精神的なメリット
・新しい技術にうまく適応できるかなどの不安を感じるなどの精神的デメリットなど
参照元:Repro「ROI(投資収益率)とは?意味と計算式、費用対効果の改善手法、ROAS・CPAとの使い分けを徹底解説」
C2H「費用対効果の評価方法」
課題②:スタッフの心理的抵抗感と教育・セキュリティの壁
コスト面以外で医療AI導入の課題となるのが
スタッフの不安感や心理的抵抗感、
セキュリティの問題などです。
前述したレセプトチェックの例を見ると、
これまで医療事務スタッフが
20時間をかけて行っていた作業を、
AIはほんの数分でミスなく行います。
医療事務スタッフにとって、
自らの存在価値を見失ってもおかしくありません。
また、スタッフの中にはAIを
使いこなす自信がないため、
導入を拒否する方が出る可能性があります。
さらに、これまでの紙での管理と異なり、
医療AI導入後はデータがPC管理となります。
クリニックの場合は院内に
大きなサーバーを置くスペースがなく、
費用面も考慮すると、
データをクラウドに置く管理が主流かもしれません。
セキュリティ管理に不慣れなスタッフは
患者さんのデータ流出を含めた
重大なリスクの可能性を考え、
クラウドや医療AI自体を敬遠する可能性があります。
解決策としては、スタッフの教育をしっかり行うことにつきます。
導入前にはスタッフの不安や要望などを
聞き取るとともに、勉強会などを通じて
「AIと共に働く」
「仕事の質を上げ、スタッフの労働の負荷を減らすためにAIを導入する」
ということを明確に伝えます。
また、セキュリティに関する意識を高め、
具体的な管理の手法を覚えることも重要です。
医療AIの導入検討の際には、
決定する前にデモを行い、
導入直後は、数か月かけて
自院で利用した場合の問題点を洗い出し、
改善を図るようにしましょう。
スタッフへは、大きな問題点がないことを
確認した上で実運用することを
あらかじめ伝えることで、
スタッフの心理的抵抗感も少なくすることができます。
まとめ
以上、クリニックで医療AIの導入が
進まない2つの理由と実践的解決策について
簡単に解説しました。
労働力人口が減少するこれからの時代、
医療AIをうまく使いこなすことで、
クリニック内の雑務の量を減らし、
医療の質を上げることができます。
また、スタッフの
ワークライフバランスを向上させ、
質の良いスタッフの定着率を
上げることにもつながります。
徐々に医療AIの機器やサービスが増え、
医療機関でも活用を検討することが多くなるかと思います。
まずは負担の少ないデモから始めて、
自院の業務に適する医療AIを探してみませんか?
医師 M.M.