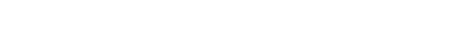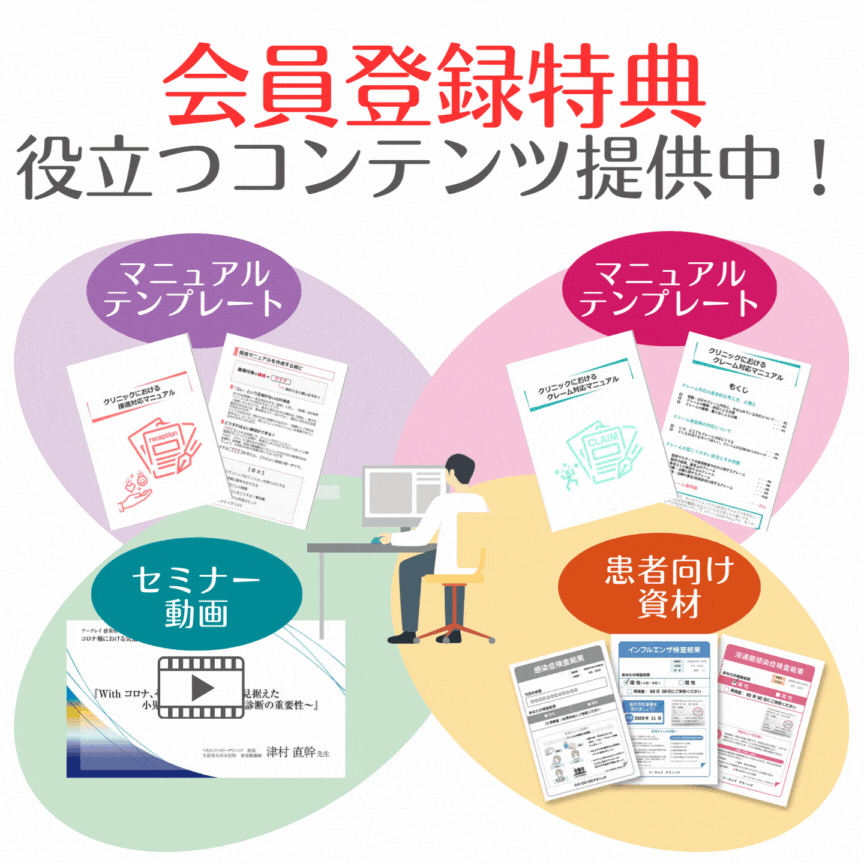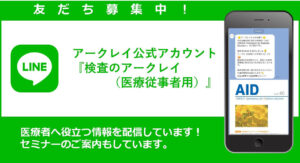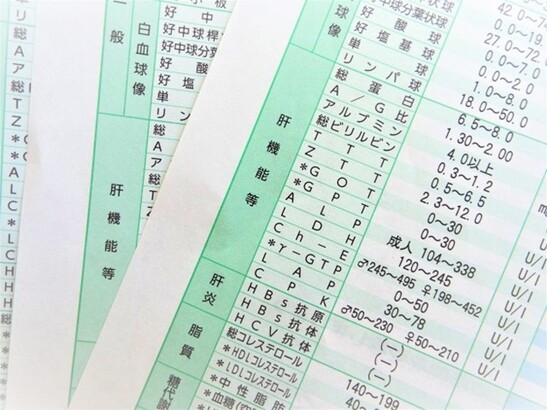
外来診療や健診で遭遇する頻度の高い
「低アルブミン血症」。
栄養不良のほか、肝疾患や腎疾患、
慢性炎症など多岐にわたる病態の
サインであることが知られています。
高齢者や慢性疾患の患者さんでは、
軽度のアルブミン低下でも
予後に影響することもあります。
そこで今回は、
関連学会ガイドラインをもとに、
低アルブミン血症で疑うべき
疾患と鑑別のポイントを解説します
低アルブミン血症とは
アルブミン(Alb)は、
血漿中で最も多い蛋白質で、
膠質浸透圧の維持や
ホルモン・薬剤などの輸送、
毒物の中和作用といった役割を持ちます。
アルブミンの基準値は4.1~5.1 g/dLで、
この範囲を下回った状態が「低アルブミン血症」です。
低アルブミン血症の背景には、
出血、消化器疾患、栄養不良、
慢性疾患、炎症、悪性腫瘍など
多様な病態が隠れている場合があります。
特に高齢者や慢性疾患の患者さんでは、
低アルブミン血症が
予後不良因子となることが知られており、
早期の原因検索が必要です。
参照元:日本臨床検査医学会「臨床検査のガイドラインJSLM2024」PDF
日本輸血・細胞治療学会「科学的根拠に基づいたアルブミン製剤の使用ガイドライン(第 2 版)」
<アルブミン検査を院内で!>
低アルブミン血症で疑うべき主な疾患と病態
低アルブミン血症において、
考えられる主な原因疾患と病態は
以下の5つです。
1. 栄養不良
アルブミンは、摂取不足や消化吸収障害によって低下します。
嚥下障害、食欲不振、独居による
食事量減少のほか、
胃切除後や炎症性腸疾患などの
吸収不良症候群も鑑別に含まれます。
ただし、アルブミン単独では
炎症や疾患の影響を受けやすいため、
総合的な栄養評価が必要です。
2. 肝疾患
アルブミンは肝臓で合成されるため、
慢性肝炎、肝硬変などの進行で低下します。
日本消化器学会・日本肝臓学会の
「肝硬変診療ガイドライン」では、
低アルブミン血症は
予後因子として重視され、
Child-Pugh分類(肝硬変の重症度分類)にも
組み込まれています。
3. 腎疾患
ネフローゼ症候群や慢性腎不全(CKD)では、
尿中への蛋白漏出により、
アルブミン値が低下します。
特に、CKDの患者さんに
低栄養、慢性炎症、心血管病の
3つが合併したMIA症候群は、
予後不良な病態を指します。
4. 消化器疾患
蛋白漏出性胃腸症では、
アルブミンの喪失が起こります。
胃ポリポーシスやびらん性胃炎、
クローン病、潰瘍性大腸炎、悪性腫瘍などが
原因疾患として挙げられます。
5. 炎症反応
感染症、外傷、手術などで炎症が起こると、
肝臓におけるタンパク質合成の
優先順位付けが行われ、
アルブミン合成が抑制されます。
また、炎症に伴う毛細血管の
透過性亢進によっても、
一過性にアルブミンが低下します。
鑑別に役立つ検査と評価方法
低アルブミン血症の
原因疾患・病態の鑑別方法は
以下のとおり4つ挙げられます。
1. 血液検査
- A/G比:グロブリン増加があれば膠原病や悪性腫瘍、多発性骨髄腫などを疑います。
- 肝機能(AST、ALT、ALP、T-Bil):肝障害や胆道疾患の評価に有用です。
- 腎機能(CRE、UN)、尿蛋白:腎疾患の評価や蛋白漏出性胃腸症の鑑別に不可欠です。
- 炎症マーカー(CRP):炎症性疾患の合併を示唆します。
2. 身体所見と病歴
浮腫、腹水、黄疸、体重減少、
食欲低下の有無を確認します。
既往歴や薬剤歴も鑑別の手がかりになります。
3. 栄養リスク評価ツール
栄養リスクのスクリーニングには
以下のツールが用いられます。
・MUST
・NRS-2002
・MNA-SF
これらのツールで
栄養リスクがあると判定した人に対し、
体重減少・筋肉量・食事摂取量・炎症の
有無を評価し、低栄養診断を行います。
4. 画像検査
腹部超音波検査は、
肝硬変所見や腹水の有無を確認でき、
腎疾患や腫瘤性病変の除外にも有用です。
低アルブミン血症の原因究明が患者さんの予後改善に有用となる
低アルブミン血症は、
栄養不良から肝疾患、腎疾患、
炎症まで多くの疾患が背景にあります。
原因を見極めて治療することが
予後改善につながるため、系統的な鑑別と
必要なタイミングでの専門医連携を行い、
早期発見・早期介入を心がけることが重要です。
看護師S.H