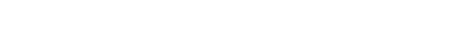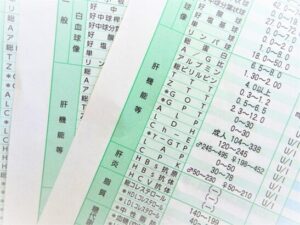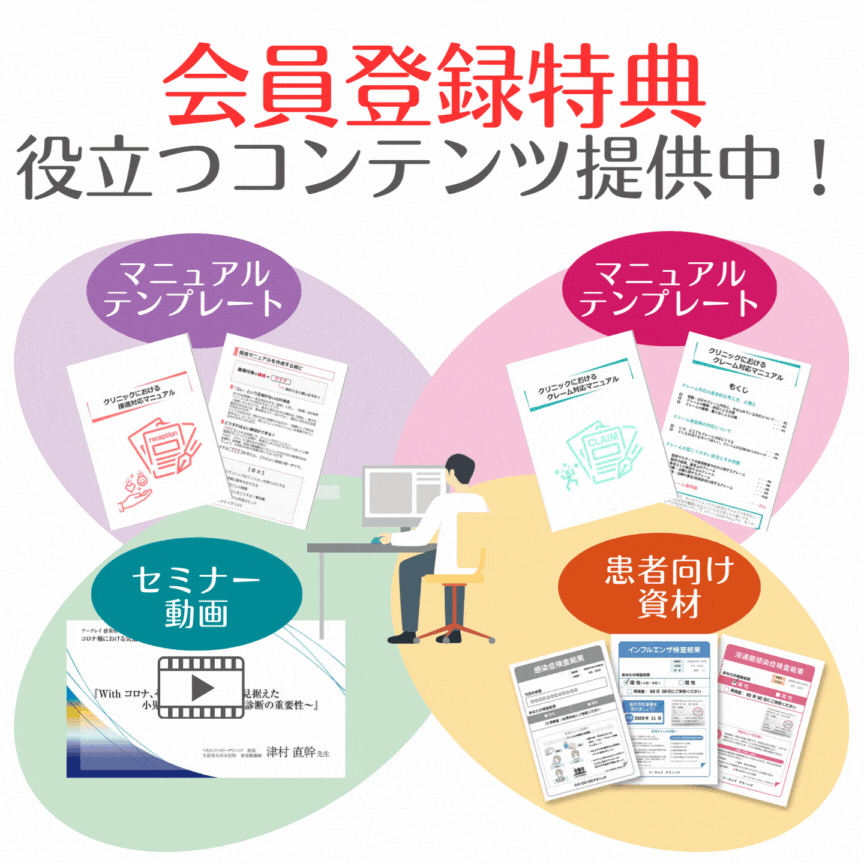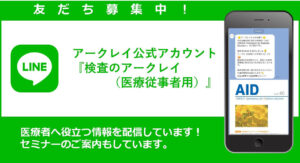毎年、秋から冬にかけては
インフルエンザや新型コロナウイルスなどの
ワクチン接種が増える時期です。
それと同時に、感染症が疑われる患者さんも
増加してくるため、
予約の電話が鳴り止まなかったり、
当日の待ち時間が長引いたりすることで、
診療全体に負担がかかるケースも
少なくありません。
スムーズに予防接種を行い、
安全性と効率を両立させるためには、
予約から実施までの一連の流れを
あらかじめ整備しておくことが重要です。
最近、厚生労働省では、
A類疾病の定期接種などの
デジタル化が進められおり、
予防接種を安全かつ効率的に
実施するための仕組みが整いつつあります。
そこで今回は、
予防接種に関するデジタル化を解説し、
インフルエンザなどの任意接種で活用できる
効率化のポイントを5つご紹介します。
「予防接種事務のデジタル化」とは?
「予防接種事務のデジタル化」とは、
自治体と医療機関等をつなぐ
情報連携システムPMH
(Public Medical Hub)と、
マイナポータル上の
デジタル予診票を活用し、
予防接種データを安全かつ正確に
連携させる取り組みです。
現在、厚生労働省では、
「予防接種事務のデジタル化」を
段階的に進めています。
昨年から、乳幼児・小児等を対象とする
A類定期接種に対して、
複数自治体で先行実施し、
データ連携上の課題整理を進めています。
また、高齢者等を対象とする
B類定期接種でも先行実施を開始し、
医療機関のタブレット等から
接種記録をPMH経由で自治体と共有する仕組みを検証しています。
デジタル化で期待される効果
・正確な接種履歴の把握
・接種間隔の自動チェック
・ロット番号の確実な記録
・自治体・医療機関の事務負担の軽減
・住民への案内の円滑化 など
デジタル化により、
重複接種や接種間隔のミスを防ぎ、
流行期にも迅速・効率的に
予防接種を進められる体制を整えることができます。
なお、冬期に流行する感染症に関しては、
高齢者のインフルエンザ定期接種(B類)が
先行実施の対象に含まれており、
デジタル予診票やPMHを通じた運用の
実装が進められています。
予防接種を効率化する5つのポイント
先述した通り、
煩雑になりがちな予防接種に関して
国や自治体では、対策として
「予防接種事務のデジタル化」などの
予防接種を効率化させる仕組み作りが進められています。
しかし、任意接種に関しては、
まだ仕組み化は進められておらず、
クリニック内で対策を検討する必要があります。
ここでは、予防接種を効率化するための
ポイントを5つご紹介します。
1. 予約の効率化はオンライン化がカギ
電話予約や当日受付のみの体制では、
受付スタッフが通常業務に手が回らなくなることも…
オンライン予約システムの導入は、
こうした負担を大きく軽減できます。
WebサイトやLINEと連携させれば、
患者さんからの予約が
24時間いつでも可能になり、
受付の混乱を防げます。
また、同時接種を選択できるよう、
項目を設けると、接種機会を逃さずに対応できるでしょう。
さらに、高齢者や基礎疾患を持つ方など
優先対象者向けの予約枠を
あらかじめ設けるのも効果的です。
午前中は高齢者、午後は小児、
といった形で時間帯を分けることで、
混雑を分散しやすくなります。
2. 問診票は事前配布で待ち時間を短縮
当日の混雑を避けるためには、
予防接種予診票や同意書を
事前に配布しておく工夫が有効です。
クリニックのホームページから
ダウンロードできるようにしたり、
予約完了メールにPDFを添付したりすることで、
患者さんは自宅で記入して来院できます。
当日は記入済みの予診票などを
提出するだけなので、
待ち時間や院内の滞在時間の短縮が可能です。
特に感染症流行期には、
院内での滞在時間を最小限にすることが
クリニックの感染対策にもつながります。
自治体によっては
複写式の予防接種予診票を採用しています。
この場合、コピーや印刷が不可な場合もあるので確認しておきましょう。
3. 接種専用枠を設定して動線を整理
診療と同時に接種を進めると、
診察室や待合室が混雑しがちです。
そこで、予防接種のための
専用の日や時間帯を設けると、
診療フローがスムーズになります。
例えば、診療前の30分、昼休みの前後、
診療終了後などに接種専用枠を設定すると、
一般診療との混在を防げます。
さらに、動線を分けることも大切です。
接種専用の待合スペースや
受付カウンターを用意すれば、
一般診療の患者さんと動線が交わらず、
院内での感染予防と混雑回避の両立が可能になります。
4. スタッフの役割分担を明確化
効率的な接種のためには、
スタッフ間の役割分担が不可欠です。
・受付は予診票などの記入確認と予約確認
・看護師は接種と説明
・医師は最終チェックと接種判断
・会計担当は次回接種の案内や説明
といった形で流れを固定化しておくと混乱が減ります。
また、業務フローをマニュアル化し、
臨時スタッフも対応できるようにすると、
繁忙期でも安定した診療が可能です。
さらに、アナフィラキシーなどの
緊急対応マニュアルを全員で共有し、
ロールプレイを行っておくと、
いざというときの不安も軽減されます。
安全性を担保する体制が整っていれば、
患者さんの安心感にもつながります。
5. 情報提供の整理・自動化で問合せ対応を減らす
予防接種の予約の電話や
予防接種に関する問合せを減らすために、
情報提供をあらかじめ整理しておくことが重要です。
クリニックのホームページに
「接種開始日」「対象者」「予約方法」
「持参物」「接種後の注意点」を
まとめたページを設けておくと、
患者さん自身が確認できます。
LINE公式アカウントや、ホームページに
自動応答チャットボットを導入しても良いでしょう。
スタッフが、患者さん一人ひとりに
電話で説明する手間が省けるだけでなく、
患者さんも安心して準備することができます。
仕組み化で効率と安全を両立
予防接種シーズンを効率よく乗り切るには、
現在の診療フローを見直すことが大切です。
オンライン予約や問診票の事前配布、
予防接種専用の時間枠の設置、
役割分担の徹底といった工夫を
組み合わせることで、
予防接種に関する業務の効率化や負担軽減、
患者さん満足度の向上を同時に実現できます。
できるところから仕組化を進めてみてはいかがでしょうか。
看護師 S.H