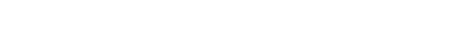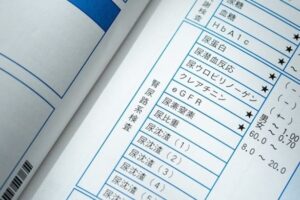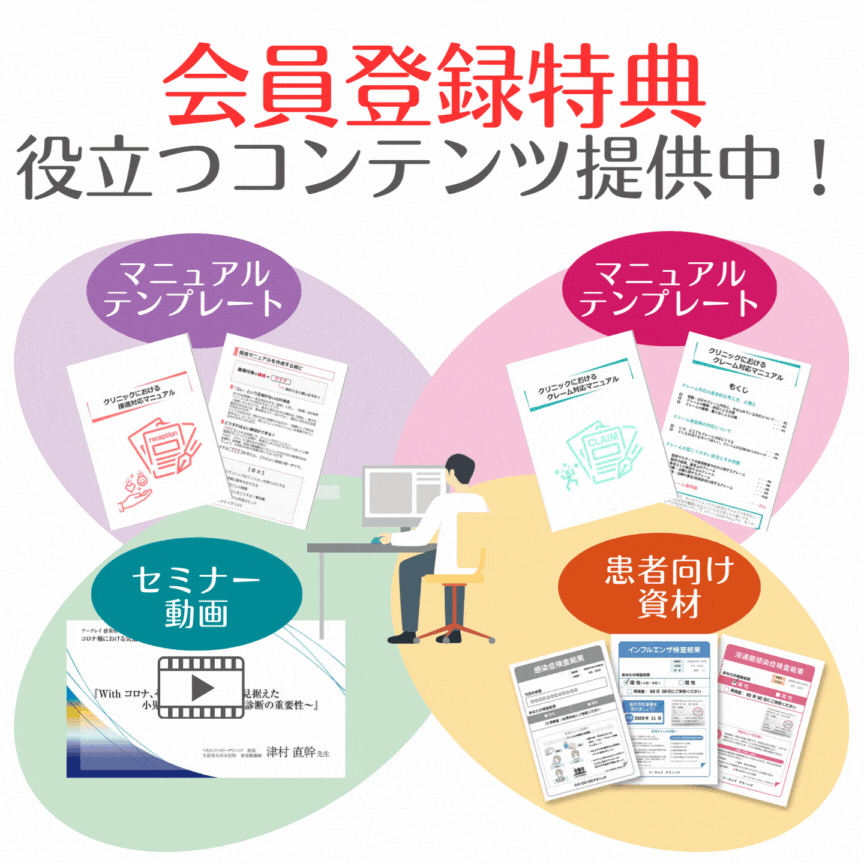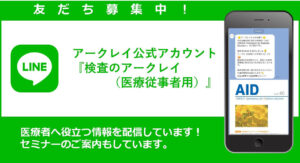患者さんに病気や薬の説明をするとき、
学会や製薬会社が作成している説明資料は
とても助かります。
しかし、本当にその資料で患者さんに
伝えたい内容を伝えることが
できているのでしょうか?
場合によっては、今お使いの説明資料の
見直し時期かもしれません。
そこで今回は、患者さん用の説明資料の
見直しに関する話題をお届けします。
万人向けの説明資料だけでよい?
一般的な患者さん用の説明資料は、
誰に対しても過不足なく情報が伝わるよう構成されています。
しかし、万人に向けた仕様は
個人の特徴に合ったものではありません。
そのため、患者さんによっては、
以下のように印象が様々かもしれません。
・ 文字が小さくて読みにくいと感じる
・ 文字が多くて途中で飽きてしまう
・ あとで読もうと思ってその存在自体を忘れてしまう
説明資料は、読んでその内容を
理解してもらって初めて意味を持ちます。
「どこが自分向けの情報かわからないし
読むのに手間がかかりそう」
と感じた患者さんは、
結局きちんと読まないで終わってしまう…
ということが起こります。
これでは説明資料の目的が達成できません。
また、1度読んで理解しても、
手元に置いて繰り返し読む、という人は少数です。
そのため、時間が経つと忘れてしまう、
ということはよくあることでしょう。
患者さんが忘れてしまった内容は
医師や看護師が再度説明することになり、
業務効率の低下にもつながります。
以上のように、
万人受けする説明資料だけでなく、
個人に寄り添った資料を用意することは、
患者さんにとってもクリニックにとっても
良い効果が期待できます。
患者さんの層に応じた説明資料とは
それぞれ患者さんにあった説明資料を
用意するためには、来院する患者さんの層を把握することが大切です。
年齢や性別、理解度、生活背景、
疾患・服薬の経験、言語・文化など
多岐にわたって分類が可能です。
考えられる患者さんの層と
説明資料のポイントをまとめました。
| 患者層 | ポイント |
| 小児 |
イラストや写真を多用し、言葉はひらがな中心。「注射はどうしてするの?」など、こども目線で問いかける。 例:絵本、マンガ、アニメ調動画 |
|
家族 |
Q&Aで整理、要点は太字・色付き、大事な数字(量・回数)は表に。 例:チェックリスト、Q&A資料、動画 |
| 高齢者 |
難しい表現を避け、手順は大きなイラストで段階的に説明。 例:大きな字の資料、イラストカードでの説明、音声動画 |
|
働く世代 |
根拠やデータを示し「なぜ必要か」を明確に。忙しい人向けに要点をまとめ、サイトに情報を公開、患者さん自身がスマートフォン等でアクセスできるように。 例:図グラフ資材・WEBサイト・短時間の動画 |
| 外国人 (日本語が苦手) |
「単語」メインの説明、「指さし会話」対応、母語での概要説明。 例:多言語資料(字幕動画)、ピクトグラム資材 |
| 健康リテラシーが低め |
1ページに1テーマ、不要な情報を省いて具体的な行動指示を伝える。 例:写真、ピクトグラム資料、行動指示のみ |
| 治療や服薬への意識が 低い・不安 |
「同じ悩みを持った人はこう乗り越えた」など共感を重視、動画はスタッフや患者さんのインタビュー形式も有効。 例:体験談動画、Q&A資料 |
他に説明資料のポイントとして、
スマートフォンを日常的に活用している人と
スマートフォンの操作に不安がある人に分かれます。
前者は動画の説明が有効で、
後者は紙媒体での説明が有効です。
動画の説明が有効な場合、
動画をクリニックのHP等に掲載し、
診察時に二次元コードなどを示せば、
あとは患者さんのタイミングで閲覧してもらえます。
説明動画の時間は3分以内にすることで、
途中離脱を防ぐことができます。
1分間の動画は180万語の情報量に
匹敵すると言われており、
短い動画でも十分説明することは可能です。
クリニック独自の資料作成のメリット
独自の説明資料を作成するには時間もコストもかかります。
その上、集患に直結するわけでもありません。
しかし、長い目で見れば以下のような
大きな効果を発揮するでしょう。
① 説明の時間の短縮による業務効率化
② 初診患者さんなどの集患
③ 患者さんへの説明の見直し
例えば、よくある質問を動画にし、
コツコツと自院のホームページ(HP)にアップするとします。
ある程度、動画が増えてくれば、
「分からないことはHPを見てくださいね」
と細かい説明をする時間を省くことができます。
患者さんは説明動画を
繰り返し閲覧することができ、
結果的に質問の減少も期待できます。
さらに医師が顔を出している場合は、
医師の紹介としても役立ちます。
初診の患者さんは先生の雰囲気を
事前に知ることができるので、
安心して来院することができます。
クリニックを迷っている患者さんは
動画をきっかけに来院を決めるかもしれません。
動画を作成する際は
「どのような人に何が伝わればよいのか」
「どうすれば伝わるか」
を考えることになります。
つまり患者さんへの説明を
見直すことにもつながるのです。
今まで当たり前のようにしていた説明を
見直すことで、診察時の対応にも変化があるかもしれません。
まとめ
普段当たり前のように使用している説明資料。
本当に患者さんに届いているでしょうか?
「説明=チラシ(紙媒体)」だけではない時代になっています。
まずは現状の患者さんへの説明内容や
使用している資料が効果的なものか、
院内スタッフで話し合うと良いでしょう。
また、患者さんの層にあった資料の作成は時間もコストもかかります。
そこで、動画作成を専門とする企業に
依頼するのもひとつでしょう。
スマートフォン上で撮影と編集が
完結するアプリもあるので、
スタッフだけで作成することも可能です。
患者さん用の説明資料は、
業務効率化や集患が期待できるため。
クリニックにあった説明方法を考えてみてはいかがでしょうか。
看護師 M.K.