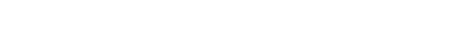選ばれ続けるクリニックには、スタッフ全員の適切な「医療接遇」が欠かせません。また、接遇の不備は評判低下やトラブルの元となります。本記事では、経営に役立つ医療接遇のメリットと、明日から使える具体的な実践方法をわかりやすく解説します。
#アークレイ
患者さんへの情報提供に重要な院内ポスターですが、「デザインに自信がない」「作成時間がない」とお悩みではありませんか?今回は、無料ツールを活用して、多忙な医療従事者の方でも短時間で簡単に、効果的なポスターを作成する方法をご紹介します。
#アークレイ
クリニック経営にトラブルはつきものですが、全て弁護士に頼るのが最適とは限りません。コストや専門性を考慮し、内容に応じて適切な士業を選ぶことが重要です。そこで今回は、トラブル別に、弁護士の他にも頼れる専門家の相談先をまとめました。
#アークレイ