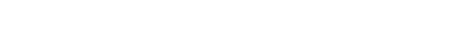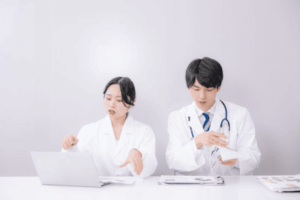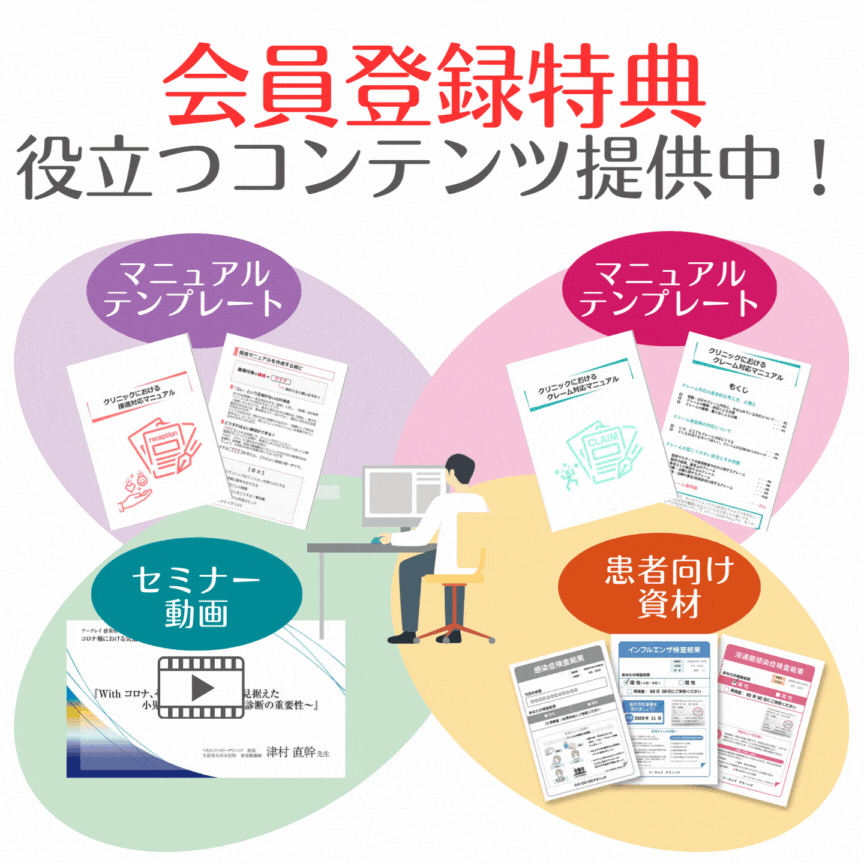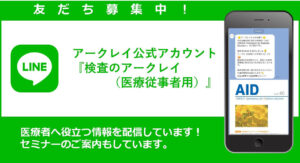2025年8月現在、
新型コロナウイルス感染者数は増加傾向で、
1医療機関あたりの6.3人となり、
感染者数が9週連続で増加しています。
参照元:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況)2025年」
新型コロナウイルス感染症や
インフルエンザなどの流行時期には、
発熱外来は非常に混雑します。
待ち時間が長くなれば、
患者さんや付き添いの家族は不満を募らせ、
クレームにつながることもあるでしょう。
そこで本記事では、
発熱外来を効率的に運用し、
患者満足度を高めるためのポイントをご紹介します。
クリニックの発熱外来運用における課題
発熱外来を運営する中で、
多くのクリニックが直面する課題として、
以下の3つが主に挙げられます。
1. 待機スペースや動線の確保
院内の感染対策のため、
通常の待合室ではなく、
患者さん自身の車内といった院外や
隔離された個別の待合室などで
待機してもらう必要があります。
また、一般の患者さんと
感染症の疑いがある患者さんの
接触を防ぐため、動線の分離も必要です。
2. スタッフの業務負担増
発熱外来を担当するスタッフは
防護服の着用や患者さんの動線の管理など、
通常診療よりも負担がかかります。
また、感染症検査のための検体採取において
感染リスクに対するスタッフの不安は
ゼロではないはずです。
3. 患者満足度の低下
発熱外来で来院した患者さんの対応に
時間がかかった場合、
通常診療の患者さんは長時間の待機をすることになります。
また、発熱外来で来院した患者さんは
通常の待合室で待機することがないため、
待合室の状況が分からず、
待機する時間が長く感じることもあるでしょう。
長時間の待機だけでなく、
待機場所や待機方法など
十分な説明がない場合も、
患者さんが不安や不満を抱きやすくなります。
発熱外来の効率的な運用ポイント
発熱外来の課題を解決し、
効率的に運用するためのポイントを
5つご紹介します。
1. 発熱外来の実施の周知
公式ウェブサイトや予約ページで、
「発熱している場合には発熱外来を受診してください」
などの案内をしておきましょう。
また、「発熱外来の流れ」や
「車内待機時の注意点」、
「持参物リスト」などを掲載することで、
発熱外来の患者さんの疑問が減り、
不安の軽減につなげることができます。
2. 予約システム・ウェブ問診表の活用
発熱外来を予約制にすることで、
患者さんの数を事前に把握でき、
待機時間を短縮できます。
また、オンライン予約時に症状や経過を
問診表に入力してもらうことで、
診察をスムーズに進める準備ができます。
3. 車内待機システムの構築
患者さんが車で来院している場合は、
院内の感染対策のため、
車内待機をお願いするとよいでしょう。
予約時や受付時に患者さんの車両番号や
車の特徴(車種やカラー)を確認し、
診察の準備が整い次第、
電話やSMSで呼び出す仕組みが効率的です。
これにより、一般診療の患者さんも
安心して来院することができます。
4. 動線の分離
発熱外来の患者さんの専用エリアを設定し、
一般診療の患者さんと動線を分けることで、
院内の感染リスクを低減します。
可能であれば、駐車場の一角に
専用のテントを設営したり、
空き部屋を活用したりするのもよいでしょう。
また、診療時間を発熱外来と
その他の外来で分ける方法や、
軽症者はドライブスルー方式で診察する方法もあります。
5. スタッフの負担軽減
感染症の検査や検査までの待機場所など
一般診療ではご案内しないことが多く発生します。
そのため、患者さんからよくある質問を、
タブレット端末やパンフレットにまとめ、
説明のための人手や時間を少なくするよう準備しておくとよいでしょう。
患者さんに寄り添った運用で信頼される発熱外来を実現
新型コロナウイルス感染症の影響で、
多くのクリニックが発熱外来を設置するようになりました。
発熱外来を効率的に運用することで、
スタッフの負担を軽減し、
患者満足度を高めることが可能です。
前述の通り、予約システムや動線管理、
待機環境の整備などを行うことで、
よりスムーズな診療が実現します。
これらの方法を活用し、
感染対策と患者さんのケアを
両立した発熱外来を目指してみませんか。
看護師 S.H.